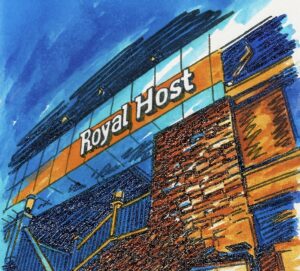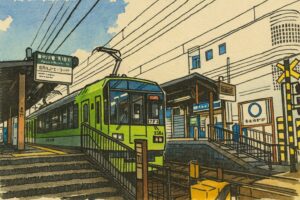京都に憧れて、2008年に地元の埼玉から思い切って移住してきた。
気がつけば十数年、今では「なんでやねん」も自然に口から出るくらいには馴染んでいる。
前回は、関東人として暮らしてみて感じた「京都ならではのメリット」を紹介したが、もちろんいいところばかりじゃなく、長く住んでると「うーん、これはちょっと…」と思う部分も出てくる。
というわけで今回は、移住してはじめて実感した京都生活のデメリット5つを挙げてみてみたので、移住を考えてる人に参考になればと思う。
『京都はどこも混雑、週末はまるでレジャー施設』

インバウンドの影響で京都市内の公共交通機関や飲食店はかつてないほどの混雑に見舞われている。
とりわけ人気の飲食店では外国人観光客の占める割合がきわめて高く、店内の七割以上を占める店舗も散見される。
飲食店の混雑は、オーバーツーリズムによる客数の急増に加え、深刻な人手不足が重なり、提供時間の遅延によって回転率が下がり、結果として行列が発生しているにすぎない店も少なくない。
このような状況で地元民が採るべき対処法は昼食のピークタイムである12時から13時を避けることに尽きる。
開店直後あるいは13時半以降に訪れれば、待ち時間なく案内される可能性は格段に高い。
筆者自身も、観光と食事のピークをずらすことで混雑を回避する「タイムシフト型」に自然と落ち着いた。
朝早くから観光を始め、11時前後に昼食をとり、12時台は名所巡りに充てる。
その後、午後のひとときに喫茶を楽しむという流れ。
もっとも、15年近く暮らして痛感するのは週末の外出を極力控えるようになったという事実である。
土日祝日に主要観光地へ足を運ぶことは混雑を覚悟することと同義である。
生粋の京都人が「嵐山や清水寺に行ったことがない」と語るのも決して大げさではなく、日常生活においては人混みを避ける合理的な判断にすぎない。
あと人が多いことにより生活面で最も負担となるのは市バスの混雑である。
観光客のみならず、通勤・通学の足としても利用されるため、朝夕の混み方は尋常ではない。
そのため筆者は自転車を新調した。
京都においてクオリティの高い自転車に乗る人が多い理由はこの事情に起因していると考えられる。
加えて、市内は意外なほどコンパクトであり、徒歩と地下鉄を組み合わせれば主要観光地を十分に巡ることができる。
観光に際しては市バスに頼らず、地下鉄と徒歩を基本とすることを強く推奨したい。
『京都の夏の暑さは想像以上』

関東出身者であっても、京都の冬は思いのほか耐えられる。
確かに早朝は底冷えが厳しく、足元から痛みを感じるような寒さがあるが、ユニクロのヒートテックの性能が飛躍的に向上していることと、近年の暖冬傾向により積雪がほとんどないから、生活していて大きな支障を感じるほどではない。
むしろ関東のほうが風が強く、体感温度としては寒さが鋭く感じられた記憶すらある。
一方で、問題は夏である。
特に8月下旬まで続く京都の暑さは、誇張ではなく「蒸し風呂」と形容するのが適切。
外で作業をすれば命の危険を覚えるほどで、最高気温39度を記録し、ここまでくると筆者自身も外出を控えている。
高温に加え湿度も異常に高いため沖縄よりも過酷に感じられるのが京都の夏。
かつては「京都は盆地ゆえに暑い」と言われながらも、まだ耐えられる範囲であった。
しかしここ数年は38度を超える日が常態化し、健康への影響すら懸念される状況となっている。
7月から8月にかけては、夜間でさえ室温が30度を下回らないのが常であり、冷房なしでの生活は現実的に不可能といえる。
そろそろ本格的にサマータイムを導入した方がよさそうだ。

これは昔から「京都あるある」として語られている。
『永住を前提に京都で仕事を探す難易度』

※この転職活動は2012年頃の内容。
筆者が前職を退職し、現職に就くまでには約1年を要した。
前職はアルバイトからの社員登用であったため本格的な就職活動はこれが初めての経験。
当時は三十代前半、前職で十年勤務し管理職も経験していたが、京都での就職活動は想像以上に厳しいものであった。
まずはハローワークへの登録から始め、並行してインターネットの就職サイトを日々閲覧していたが、東京との決定的な違いは求人件数の圧倒的な少なさである。
特に目立つのは観光関連や介護施設での募集であり、ホテルや土産物店、飲食店などの職種が大半を占める。
商社や大規模企業の求人はごく限られており、名の知れたチェーンやブランドの募集も存在するが、転勤の可能性が高く「京都永住」を条件としていた筆者にとっては適合しなかった。
また、京都ならではといえるのが老舗企業の求人である。
歴史ある名門企業の募集に心惹かれるものの、よく見ると同じ求人が毎月のように繰り返し掲載されており、離職率の高さか過酷な採用条件が背景にあるのではないかと、安易に飛びつくのは危険と判断した。
さらに京都市役所関連の募集も多いが、その多くは臨時職員としての単年度採用であり、嘱託職員へのステップアップはあっても正規職員登用は極めて稀である。
正規職員と同等の業務を担いながら待遇に大きな差があることはよく聞かれる話であり、期待を抱きにくいのが実情である。
そうした厳しい状況の中でも、最終的に筆者は就職先を得ることができた。
しかしその過程は決して容易ではなく、アルバイトとしての採用から始まり、契約社員を経て、正社員登用までに実に五年を要した。
こんな感じで京都市内で働けて、なおかつ転勤がなく京都永住を条件にするとガクンと仕事が見つからなくなってしまうのである。
『関東と比べて実感する京都の生活コスト』

筆者の生まれ故郷である埼玉と比べるとやはり京都の物価や家賃は高いと感じる。
特に賃貸契約に際して発生する「礼金」は異様に高額である。
不動産業者によれば、京都は建物の高さ規制や景観規制によって新築が制限されており、更地も少なく供給が追いつかない。
そのためアパートやマンションの数自体が限られており、加えて一度契約すると住み替えが少ないため回転率も低い。
そうした事情が礼金高騰の背景にあるのでは、とのことであった。
筆者自身も、会社都合で引っ越した際に家賃7万円の物件で礼金30万円を支払った経験がある。
関東では「家賃1か月分」が相場であったため、初めて耳にしたときは高額であることにびっくりした。
物価についても埼玉に比べるとやや割高である。
もちろん京都にも激安スーパーや業務用スーパーは存在するが、長く住むとつい「本物」に目覚めてしまう。
近所の名店のパンや焙煎珈琲、職人の手による豆腐や納豆、さらにはこれまで縁のなかった和菓子にまで関心が広がり、いつしか嗜好は「質」へと傾いてしまった。
その結果、四人家族で食費が十万円を超えることもしばしばであり、外食も個人経営のオーガニック系の店を選ぶことが多く、一度の食事で1万ぐらいに達することもある。
もっとも、日常生活においては無理にお金をかけずとも満足できる術を身につけたため、「せめて食事くらいは」という考えから今のところ改善するつもりはない。
京都は職人気質が息づく土地柄ゆえ、日常的に「本物」に触れる機会が多く、結果的に生活コストが高くつく街であるといえるのかもしれない。
『関東人の悩み?京都のうどんだしに慣れない』

この項は、いわば「おまけ」として挙げておきたい。
メリットを五つ列挙した手前、数を揃えるためにデメリットも並べてみたものの、実のところ致命的な不満があるわけではない。
それは「うどんの味」である。
筆者にとってのソウルフードは、甘辛く真っ黒なつゆに浸った関東風のうどんであり、いわば「富士そば」の味が基準である。
対して関西のうどんは澄んだ出汁に上品な薄味が特徴で、確かに香り高く洗練されているのだが、どうしても物足りなさを覚えてしまう。
そうした中で、京都に移住してからは「関東風のうどんつゆ」を自作する術を身につけた。
出汁は京都の老舗〈うね乃〉の出汁パック「赤じん」を用い、そこに工夫を加えることで、ようやく自分の舌に馴染んだ“富士そばのつゆ”を再現できるようになったのである。

もっとも、この「関東風のつゆ」は筆者の舌には馴染むものの、関西出身の妻には不評で、家庭内でも東西の味覚差が垣間見える瞬間である。
『最後に…』

とはいえ、京都への移住はメリットが非常に多く、デメリットはさほど気にならない。
特に、お金をかけずとも充実した生活が送れる点は埼玉ではなかなか得られなかった感覚である。
他府県から京都移住を考えている人がいたらそこまで深刻にならずとも良いのではとアドバイスをしたい。
▶︎京都のささやかではあるが魅力的なスポットや過ごし方について紹介↓
https://sazmism-kyoto.com/kyoto-petitmerit/京都観光の強い味方「地球の歩き方 京都」↓