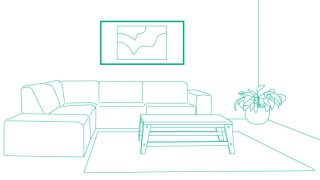今回は、京都に移住して気づいた「地味に良かったこと」をテーマに、暮らしの中でふと感じた小さな幸せをまとめてみた。
観光では気づけない、住んでこそ実感できる京都の魅力。
これから京都に移住を考えている人の参考になればうれしい。

筆者紹介・・・埼玉県生まれ。京都に憧れて2008年に移住。京都検定2級保持者で休日はもっぱら京都でフィールドワークに勤しむ。好きな場所は鞍馬寺と高山寺と朝イチの哲学の道。
豆腐の美味しさが別格

大徳寺のすぐ近くという立地も相まって街の空気にしっくり馴染むたたずまい。
京都の豆腐がなぜ美味しいのか?
京都といえば湯豆腐、というイメージは昔からあったけれど、実際に京都に住んでみて「これは本当に美味い」と思わされた食材のひとつが豆腐。
その理由は、良質な地下水。
北大路魯山人も「京都には良水があるから豆腐がうまい」と語っているがまさにその通りだと思う。
京都に移住してから、一人で湯豆腐をよくするようになった。
スーパーに行けば地元の老舗豆腐店の品がずらりと並んでいてしかも種類も豊富。
なかには創業100年を超えるような豆腐屋もあり、個人経営の店も普通に地域に根付いている。
しかも驚くのはその価格で、老舗ブランドの豆腐が250円前後で買えることも珍しくなく、高級料亭や旅館で出てくる豆腐とまったく同じものが家で食べられる。
大手メーカーの豆腐と100円の差でそのクオリティが味わえるなら迷わず老舗を選ぶ。
関東にいた頃には味わえなかった「豆腐」というごちそうを京都では気軽に味わうことができる。

価格も手頃で、味はしっかり京都クオリティ。
特にお揚げとの相性が抜群で、味噌汁に入れると一気に贅沢感が増す。

高級料亭や老舗旅館にも豆腐を卸している、いわば“プロ御用達”。
地域に銭湯文化が根付いている
京都の銭湯はまるで神出鬼没。
風情ある住宅街を歩いていると「え、こんな場所に?」と思うようなところに、昔ながらの銭湯がぽつんと現れる。
なかでも別格の存在とされているのが京都市北区・鞍馬口にある船岡温泉。

その美しさから「裸で見る美術館」なんて異名もある「船岡温泉」。
そんな風に道を歩けば銭湯に出会う京都。
実際、筆者の家の近所にも徒歩圏内に3軒の銭湯があって月に3〜4回は通っている。
やっぱり大きな風呂に入るってそれだけでちょっとした贅沢。
しかもお湯がしっかり熱い。
昔、東京・上野の下町銭湯で火傷寸前の熱湯に入った記憶があるけれどそれに匹敵するくらい熱い。
その熱さに耐えながら浸かる時間がなんとも言えない気持ちよさだったりする。
そして、京都の銭湯カルチャーを盛り上げてくれているのがゆとなみ社。
「銭湯を日本から消さない」をスローガンに、代表の湊三次郎さんを中心とした若手メンバーが、現代の感性で銭湯をアップデート中。

朝風呂が可能なこともあり筆者もよく利用しているお気に入りの銭湯のひとつ。
青葉市子の銭湯ライブが行われたこともある。

熱い湯船に浸かる時間が1日の疲れをほどいてくれる。

なかでも驚いたのが、あの小山田圭吾ことCORNELIUSとのコラボによる限定タオルの販売。
京都への移住を考えるなら、近所に銭湯があるかどうか――それも意外と重要なチェックポイントかも。
パン屋がコンビニぐらいある
京都はとにかくパン屋が多い。
感覚的にはコンビニと同じくらい街中に点在している気がする。
移住前はパンはほぼコンビニで買うものでパン屋に行くことは年に数回あるかないか。
でも京都に住むようになってからは自然とパン屋に足が向くようになった。
理由は簡単でパンのクオリティが圧倒的に違う。
一度体験するともうコンビニのパンには戻れなくなる。
おかげでちょっと健康的になった気もしている。
また、京都のパン屋はチェーンよりも個人経営の店が圧倒的に多いのも特徴。
とはいえ、地元の名店・進々堂や志津屋といった老舗チェーンも美味しいから侮れない。


2018年、長年の卸専門から一転し、左京区・松ヶ崎に実店舗を構えたことで話題になった。
その完成度の高さについ買いすぎてしまうこともあり、
筆者も気づけば3,000円超えの買い物をしてしまうこともある。

中でも看板商品は、予約必至の「食パン」。
その人気ぶりは凄まじく、基本的に予約分で完売してしまうため店頭に並ぶことはほとんどない。
ただ、まれに店頭販売されていることがあり、
もし見かけたときは荷物になろうとも迷わず購入したい一品。

昭和レトロな佇まいと昔ながらの製法を守るコッペパンで
地元民はもちろん観光客にも圧倒的な人気を誇る。
観光シーズンには朝から行列ができるほどの人気だが並ぶ価値は十分にあるクオリティ。
パン好きを自認するなら一度は足を運ぶべき京都の名店のひとつ。
京阪電車が快適

有料級の快適さ
埼玉で埼京線や東武線に揺られていた身からすると京阪電車はまさに超快適の象徴。
特に魅力なのが、始発駅―出町柳―から終点―淀屋橋―までずっと座り続けられるボックスシート。
出町柳で座席を確保し、淀屋橋までの約54分の間に文庫本が一冊読めてしまう贅沢な時間。
同様に帰りも始発の淀屋橋から座って帰れるから快適さが保証されている。
それだけでも十二分に満足できるのに、+500円で乗れるプレミアムカーではさらなる快適さが待っている。
京阪電車のプレミアムカーは、特急列車のうち1車両だけが“有料指定席”として運用されている特別な空間。
“移動”を“休息”や“集中”の時間に変えてくれるプレミアムカー、たった500円で手に入るこの快適さは、知ってしまうと普通席にはなかなか戻れない。


膝上でも作業しやすい簡易テーブル、そして全席に電源完備。

淀屋橋駅内にあるアンスリーで大起水産の寿司を購入。
1人席なら気兼ねなく食事も可能。
京都の癒しスポット鴨川
京都人の憩いの場「鴨川」との暮らし
京都市街を南北に流れる「鴨川」は、京都人にとっての癒しスポット。
今出川・出町柳あたりでY字に分かれ、上賀茂方面は「賀茂川」、大原・鞍馬方面は「高野川」と呼ばれている。
かつて鴨川は、頻繁に氾濫を繰り返す“暴れ川”として知られていた。
権力者であった白河法皇が「天下三不如意(自分でも思い通りにならないもの)」として挙げたのが、
「賀茂川の水・双六の賽・山法師(延暦寺の僧侶)」というのは有名な話。
今では治水が整備されそんな心配もなく安心して過ごせる場所へと変わったので安心。
京都に移住してから、「暇だしとりあえず鴨川へ」という日が増えた。
読書、瞑想、食事、昼寝、ランニングや散歩。
気分に合わせて、鴨川との付き合い方を変えられるのが魅力。
筆者は、小型レジャーシートとキャンプ椅子を持参してぼんやり読書しながら、コーヒーを片手に川の流れを眺めて過ごすのが定番の過ごし方。

その2つの河川が合流して市内に流れていくのが鴨川。

地元目線のおすすめはこここ北大路〜北山通あたりの鴨川。
人も少なく、木陰も多い。自然の近さをよりダイレクトに感じられる

賀茂川のベンチで食べるのも定番の過ごし方。
鴨川の近くに住むという贅沢
鴨川に気軽に通える距離に住めば暮らしの質が確実に上がる。
すぐに“日常から離れられる場所”があることがどれだけ贅沢かを実感する。
京都に移住するなら「鴨川に歩いて行けるか」は、物件選びの大事な判断基準になる。
贅沢な朝活時間を満喫できる
京都の朝は、ちょっと特別。
京都の朝は早い。
そして、驚くほど清々しい。
観光を楽しむにも、街を感じるにも、動き出すならお店が開く10時からじゃ遅い。
7時台には外に出ていた方が断然いい時間が過ごせる。
たとえば平安神宮や清水寺などの有名寺社は朝7時ごろから拝観可能。
混雑ゼロ、空気も澄んでいて、まるで自分だけの特別な京都が広がっているような感覚になる。
筆者は朝8時頃にランニングに出ることが多く、哲学の道や平安神宮のあたりを走る。
その時間帯、観光客はぽつりぽつりとしか見かけない。
特に快晴の日は空気が澄みきっていて、身体も心もリセットされるような感覚。

人がまったく写り込まない写真が撮れる貴重な時間帯。
昼間なら観光客でごった返す境内もこの時間は驚くほど静かでまるで貸切。

観光客の姿はほとんどなく、朝の空気が格別に清々しい。
そしてグルメ狙いの人にも朝活はおすすめ。
開店直後の人気店なら行列に並ばずサクッと入れる。
老舗の喫茶店は朝7時から営業しているところも多くモーニング文化も楽しめる。

町家をリノベーションした落ち着いた空間で、
京都らしい朝時間をゆっくり楽しめる“京都スペシャル”な一軒。

今回は、京都に移住してから気づいた「地味に良かったこと」を紹介してみた。
気づけばもう17年以上も住んでいるけれどいまだにツーリスト気分が抜けない。
夏は暑くて冬は寒くて、観光客も多くて…と不便なこともあるが、それを補って余りあるだけの魅力がある。
そんな「地味に良かったこと」が日常のすぐそばにあるだけで「移住してよかった」と思える。