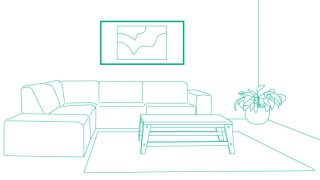本格的な紅葉シーズンが始まる直前の11月上旬、ザ・リッツカールトン京都の〈ザ・ロビーラウンジ〉で、ピエール・エルメ・パリ監修のアフタヌーンティーを体験してきた。
普段はアメックス・マリオット・ボンヴォイカードの無料宿泊特典を使って、年に一度ほど〈ザ・リッツカールトン大阪〉に泊まることがあるけれど、京都のリッツは今回が初めての訪問。
国内に5軒あるリッツの中でも京都は圧倒的に宿泊費が高く、とりわけ紅葉シーズンともなれば1泊20万円超えは当たり前で京都のホテルの中でもぶっちぎりでラグジュアリーな存在。
当然、今の自分の収入で気軽に泊まれるような場所ではない。
でも最近、密かにハマっているのが「一流」体験。
一流のラーメン、一流のうどん、一流の本屋──そんな身近な“いいもの”を楽しむブームが自分の中にあって、今回はその延長線上で「超一流の空間」と「超一流のサービス」を体験してみようという流れになった。
スターバックスのドリップコーヒー約20杯分──そう聞くとちょっと腰が引ける価格帯だけど、それだけの価値があったのも事実。
美しく設えられたラウンジ、細部まで気配りの行き届いた接客、そして目でも舌でも楽しめるピエール・エルメのスイーツで、非日常の極みのような時間をほんのひととき味わえた。
自分の“今”の背伸びが届く範囲で一流に触れる。
そんな体験の積み重ねが日常の見え方をちょっと変えてくれる気がしている。

ザ・リッツカールトン京都は鴨川沿いで二条大橋のたもとに佇む地下2階・地上5階建てのホテル。
全134室の客室を持ち国内外のラグジュアリーホテルの中でもとりわけ高い評価を受けている。
もともとこの地には藤田観光が運営していた「ホテルフジタ京都」が営業していたが2011年に閉館。
2014年に新たに建て替えられ、ザ・リッツカールトン京都として生まれ変わった。
鴨川沿いをジョギングするのが習慣になっているが、リッツの建築はその景観に見事に溶け込み、目立つことがまったくなく、京都の山紫水明を損なわずに存在するそのたたずまいは、この街に対する深い敬意を感じさせる。
入り口も町家風にこじんまりしていて、「本当にここが京都随一のラグジュアリーホテル?」と疑いたくなるほど控えめ。
そのせいか、地元の人でもリッツがこの場所にあることを知らない人は意外と多いし、ホテルフジタ京都の“リニューアル”だと思っている人もいるかもしれない。
そんな慎ましやかな佇まいに安心して軽自動車で乗りつけてみたら、駐車場入り口には高級外車がずらり。
しかも、スタッフが丁寧にバレーサービスで案内してくれて思わず顔が赤らんだ。
今回予約したのは、ザ・リッツカールトン京都の〈ザ・ロビーラウンジ〉で楽しめる、ピエール・エルメ・パリ監修のアフタヌーンティー。
公式サイトから事前予約していたが非常に人気が高く飛び込みだと席が取れないこともあるらしい。
制限時間は2時間。
12時スタートの回を予約していたが時間的にはちょうどよく、落ち着いて楽しめる長さだった。
ドレスコードはスマートカジュアル。
自分は清潔感のある“きれいめユニクロ”でまとめてみた。
少し緊張しながら町家風のエントランスを抜けまるで行き止まりのような通路の先にある巨大な自動ドアが開いた瞬間、一気に視界がラグジュアリーに切り替わる。
3メートルごとに「映え」ポイントが出現するような、美しく計算された空間構成に思わずカメラを構え、気づけば入店早々、撮影タイムが止まらない。


ザ・ロビーラウンジは、あの巨大な自動ドアがゆっくりと開いたそのすぐ先に広がっている。
京都の町家建築を意識した空間デザインで天井は高く庭園側は一面ガラス張りで自然光がやわらかく差し込み、外とのつながりを感じられる開放的な設えになっている。
重厚な雰囲気はありつつも空間に圧迫感はなくむしろ肩の力が抜けるような落ち着きがある。
高級ホテルのラウンジにありがちな「構えてしまう感じ」がなくとても居心地がいい。
ザ・ロビーラウンジには宿泊エリアとの明確な仕切りがないため、店内に一歩足を踏み入れるとすぐにスタッフが気づき、丁寧にテーブルまで案内してくれる。
このスムーズな導線も、リッツならではの洗練を感じさせるところ。
案内されたテーブルには、まるで高級レストランのコースディナーが始まりそうなほどしっかりとしたセッティングが施されていて正直ちょっと焦る。
スタッフの対応は終始丁寧で穏やか。
格式高い空間でありながら自然とくつろげるムードをつくってくれているのが印象的だった。

ザ・ロビーラウンジに着席してまず気になったのは周囲の客層。
さりげなくキョロキョロと周りを観察してみると男性客は自分ひとりくらいで、目立っていたのは外国人観光客や日本人の30〜40代女性による優雅な女子会といった雰囲気。
平日昼下がりということもあってかこちらが勝手に想像していたような“エグゼクティブ感”あふれるビジネス層の姿はあまり見かけなかった。
やや場違いなような気がして落ち着かずつい視線があちこち泳いでしまう。
そんなもじもじしたタイミングで、ウェルカムドリンクが登場。
しょうが風味のお茶でほんのりスパイシーながらもさっぱりとした味わい。
緊張で乾いた喉にちょうどよく気がつけば一気に飲み干していた。
今回のアフタヌーンティーは、紅茶、緑茶、ハーブティー、コーヒー、さらにはチョコレートドリンクなど、種類豊富なドリンクメニューから好きなものを2種類選べてしかも飲み放題という嬉しい内容。
その中から選んだのは名前に惹かれてしまった「スモークドチャイナ」と「リッツカールトンブレンド珈琲」。
どちらも初体験のメニューで、味がどうこうよりも、“選ぶ時間”そのものがすでに非日常を味わう一部になっていた。

続いて運ばれてきたのは、アフタヌーンティーの甘くない部門──いわゆる「セイボリー」。
一口サイズながらしっかりとした味わいと満足感がある。
スタッフが一品ずつ丁寧に説明してくれるのも嬉しいポイントで、料理に対する期待がじわじわと高まる。
ただ、慣れないフォークとナイフに少々手こずり、後半は潔く手でいただくことになる。
一口でパッと食べてしまうにはあまりに惜しく、二口、三口に分けてゆっくりと味わう。
それぞれが普段の生活ではなかなか出会えないような洗練された味ばかりで、ハレの日以外では味わうことができないような美食を十二分に堪能する。

「京都産バターナッツのタルトレット」「グジェールトリュフ風味茸のマリネ」
「サステナブルサーモンマリネとグリーンレモンの砂糖漬け」「自家製マグロのコンフィと胡瓜サンドイッチ」
テーブルに着いてからおよそ30分、いよいよアフタヌーンティーの主役とも言えるスイーツが登場。
三段のティースタンドに美しく並んだスイーツに思わず見とれてしまう。
だが、ここでちょっとした“戸惑い”が訪れる。
テーブル上にはすでにお皿がセットされているのだがスイーツをタワーから直接その皿に取るべきか、それとも一品ずつケーキ皿に移して食べるのがマナーなのか…という地味に深い問題。
そんな迷いが顔に出ていたのかスタッフさんがさりげなく声をかけてくれた。
「はじめに温かいスコーンをお皿に移してお召し上がりいただき、その後、お皿ごとスイーツをお取りいただくのが、当ラウンジでのおすすめのスタイルでございます」
おかげで皿の上に皿を乗せるという恥を掻くこともなくやもやしていたお皿問題が解決された。
こうした細やかな気配りがあるからこそラグジュアリーホテルのアフタヌーンティーは特別な体験になるのだと、あらためて実感する瞬間だった。


「チーズケーキプレニチュードサブレ生地」「チョコレートチーズケーキ ソフトキャラメル」
「チョコレートマスカルポーネクリーム」「エモーションイスパハン」
普段は和菓子以外ほとんど甘いものを食べない自分にとって、アフタヌーンティーはまさに一年分のスイーツを味わうような体験だった。
美しくて繊細なスイーツをじっくり堪能し満足感に浸っていたところへさらにマカロンとチョコレートが登場。
「さすがにもう甘いものはいいかな」と思いつつも、なぜか不思議とするっと食べられてしまう。
甘さのバランスが絶妙で最後まで美味しく楽しむことができた。

スイーツタイムはおよそ1時間。
残りの1時間は優雅な空間と心地よい余韻に身を委ねる。
昼食は抜いていたがこのアフタヌーンティーだけで、食事としても十分すぎるほどの満足感があった。
今回訪れて一番印象に残ったのは、料理やスイーツ、ドリンクのクオリティの高さ以上に、スタッフの接客レベルの高さだった。
以前読んだ、高野登著『リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間』に書かれていた“あの接客”が、目の前で自然に繰り広げられていた。
特に驚いたのが、こちらが「すみません」と声をかける前に、スタッフが常に気づいて寄り添ってくれること。
マナーに不安があっても、おかわりを頼みたくても、トイレの場所が気になっても──何か少しでも迷いがあれば、すぐに誰かが自然にサポートしてくれる。
その気配りが店内の隅々まで行き届いていてとても感動した。
写真を撮る際も快く対応してくれただけでなく、「こちらがケーキと一緒にきれいに写るおすすめの位置です」と、さりげなく提案までしてくれる心配りも。
今や多くの飲食店で非接客の電子端末オーダーが当たり前になりつつある中で、ここでは“人”の力による丁寧なおもてなしが体験できる。
その価値は金額以上に大きいと感じた。
お値段以上の体験。
その余韻は数日経った今でもまだふんわりと続いている。
⇩ザ・リッツ・カールトン東京に宿泊した感想