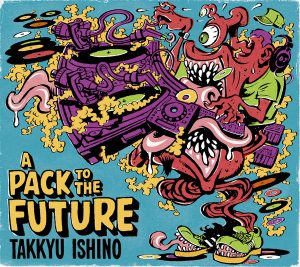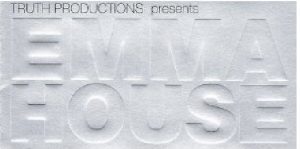2022年、アンビエント・ミュージックの創始者ブライアン・イーノの展覧会「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」がさらにスケールアップした第2弾「AMBIENT KYOTO 2023」が開催された。
今回の参加アーティストは、故・坂本龍一、高谷史郎(ダムタイプ)、CORNELIUS、BUFFALO DAUGHTER、山本精一という錚々たる顔ぶれ。
会場は、通常は立ち入ることのできない「京都中央信用金庫 旧厚生センター」と「京都新聞ビル地下1階」。
いずれも歴史や意外性に満ちた空間。
これらの空間を舞台に、日本屈指のサウンドエンジニア・ZAK氏が設計した立体音響、そして高田政義氏による照明がシンクロ。
音、光、映像が溶け合う「体験型」のアート展が誕生した。
アンビエント・ミュージックには正直なところそれほど明るくない筆者sazmだが、秋晴れの心地よい昼下がり、期待に胸を膨らませ「AMBIENT KYOTO 2023」へと足を運んできたので、会場の空気感やその体験をレポートしたい。
EXHIBITION 01 / 坂本龍一+高谷史郎 asynchronous-immersion 2023


京都新聞ビル地下1階の会場は、2015年まで実際に稼働していた印刷工場の跡地。
普段は一般公開されていない場所で、足を踏み入れるだけでも特別感がある。
油やインクの残り香がわずかに漂うその広大な空間は、天井高が約10メートル、まさに工場跡地ならではのスケール感。
そこに設置された大画面では、坂本龍一と高谷史郎のコラボレーション映像が静かに、しかし力強く映し出されている。
音響設計はこの空間の奥行きや高さを最大限に活かすよう緻密に計算されており、坂本龍一の『async』が持つ繊細な響きを余すところなく体感できる。
ピアノや弦、雨の音など、一音一音が空間に溶け込むように響き渡る。
その音に寄り添うのは、高谷史郎が日本、ドイツ、アイルランド、アメリカ各地で撮影した映像。
音と映像が静かに呼応し合い、観る者の時間感覚をゆっくりと溶かしていくような没入感があった。



イヤホンで聴くのとはまったく別物。
広大な空間で鳴る『async』は、音色の余韻や音の“間(ま)”が際立ち、耳だけでなく体全体でその響きを感じ取ることができる。
作品の上映時間は約1時間。
事前に『async』をしっかり聴き込んでから会場に足を運ぶことを強く勧めたい。
自分の記憶にある『async』と、空間に満ちる生の『async』。その違いに気づくことで、作品の新たな側面や魅力に触れられるはず。