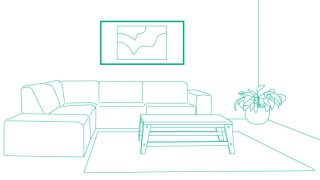弱冠22歳の田中フミヤが石野卓球プロデュースによって完成した日本初のDJ MIX CD
1995年4月リリース。
18歳で大阪を拠点にDJをはじめて20歳の頃に自らのレーベルとれまレコードを設立。
その頃にはジェフ・ミルズやローラン・ガルニエ、デリック・メイなどの海外の大御所DJと共演を果たすなど密度の濃すぎる4年間を経てリリースされたのがこの「アイ・アム・ノット・ア・DJ」。


1 FUMIYA TANAKA / ANIMAL ATTACK
2 PURVEYORS OF FINE FUNK / MIDNIGHT ENCOUNTER
3 FUTURE LEGEND / THE WHIP
4 DENKI GROOVE / DINOSAUR TANK
5 ROBERT ARMANI / ROAD TOUR RMX
6 ODYSSEY NINE / VAMP
7 PLANETARY ASSAULT SYSTEMS / STARWAY RITUAL
8 MILLSART / STEP TO ENCHANTMENT
9 CYRUS / ENFORCEMENT
10 JEFF MILLS / CHANGES OF LIFE
11 THE SABRES OF PARADISE / DUKE OF EARLSFIELD
12 DJ HELL / LIKE THAT
13 PHYLYPS / TRAK RESHAPE
14 MAURIZIO / PLOY
15 VAINQUEUR / LYOT
16 LFO VS F.U.S.E.
17 BFC / GALAXY
18 G-MAN / BIO-FIDELIC
19 LFO / TIED UP
20 DJ SKULL / NUCLEAR FALL OUT
21 F.U.S.E. / TRAIN TRAC
22 FUMIYA TANAKA / BILLY
23 SPAWN / TENSION
24 ROBERT HOOD / MUSEUM
25 SULFUREX / POINT BREAK
テクノが最も“テクノらしかった”時代の空気をそのままパッケージしたような一枚。
田中フミヤの数あるMIX作品の中でも、ここまでハードミニマルに振り切った内容は、本作と『MIX UP Vol.4』くらいしかない。
中でもこの作品は、ハードミニマルテクノのビートが熱気に包まれたフロアを容赦なく叩きつけるといった表現が相応しいくらいハードな内容。
Distortion時代のフミヤ氏を知る人ならきっと胸が熱くなるはず。

オープニングを飾るのは、田中フミヤ自身のトラック「ANIMAL ATTACK」。
ヒップホップ由来のサンプリング手法を取り入れたブレイクビーツで、独自の空気感を一気に立ち上げる。
序盤はアイドリングのようなフロアをじわりと暖めるような選曲が続くなか、起爆剤として投入したのが電気グルーヴ「DINOSAUR TANK」。
たたみかけるように繰り返されるシンセのループが抜群の中毒性を放ち、今聴いても全く色褪せないフロア直結のキラーチューン。
限定アナログ「ドラゴンE.P.」に収録されていたこの一曲は、ここで初のCD化となり当時大きな話題を呼んだ。
シカゴ・アシッド・テクノの重鎮ROBERT ARMANI「ROAD TOUR」を選曲し一気に攻めのモードへと転じていく。
UKテクノ界の重鎮ルーク・スレイターによるハードミニマル名義Planetary Assault Systems。
90年代の“良い時代”のテクノを象徴するような、硬質なキックと鋭く刻まれるハットが腰にズシンと響いてくる。
このMIX CD最大のピークポイントがこのJEFF MILLS 3連発!!
JEFF MILLS最大のフロアキラーとも言える「Step to Enchantment」からBasic Channelの記念すべき最初のシングルCyrus「Enforcement」JEFF MILLSリミックスをフロアを煽るような攻撃的ミックス。
そして極めつけは「Changes of Life」のロックの魂すら感じさせるピアノリフのカットイン。
この選曲とミックスが個人的にこのCDのピーク。
JEFF MILLS3連発でフロアに充満した熱気をほんの少しクールダウンさせるように、アンディー・ウェザーオール率いる看板ユニットThe Sabres of Paradise「Duke Of Earlsfield」を選曲。
ここで選曲のテンションに変化を持たせ、アシッドやハードミニマルの高揚から、次のピークに向けてフミヤ氏の新たな世界観が広がる。
ドイツ・ミュンヘンが生んだ伊達男、DJ Hellによる「Like That」。
無骨で硬質なビートにヴォイスループを巧みに用いたこのトラックで、フロアを少しずつ過熱させていく。侵食していく。
ベーシック・チャンネル始動以前、モーリッツ・フォン・オズワルドが手がけた初期プロジェクトMAURIZIO。
のちのミニマル・ダブの源流を感じさせつつも、この頃はまだ90年代テクノ特有の“鳴りの良さ”が前面に出ている。
続くVAINQUEURの「Lyot」を手がけたのも、同じくMAURIZIOによるリミックス。
ここからの2曲はいまもなおフロアでプレイされているテクノの金字塔。
LFOとリッチー・ホゥティンの共作「Loop」は、シンプルな構造の中に緊張感と中毒性を兼ね備えたミニマル・グルーヴの傑作。
続くはカール・クレイグによる初期名義BFCで発表された1990年のクラシックス「Galaxy」。
名門レーベル「Warp」の看板アーティストとしてシーンを牽引したLFOによる、ブリープ・テクノの真骨頂「Tied Up」。
鋭くも肉厚なベースラインとミニマルで硬質なシンセが交差するサウンドは、90年代UKテクノの空気をそのまま閉じ込めたような一曲。
この曲なしにWarpの初期は語れない。
ここから先はフィナーレへ向けて一切ブレーキなしのハードミニマルラッシュ。
骨太な4つ打ちが地鳴りのように押し寄せ、シカゴ・アシッドの血脈を継ぐDJ SKULLが放つBPM140超えのブリブリなアシッド・トラック「Nuclear Fall Out」。
音圧、速度、鋭さ──すべてがピークを更新していく、まさにクライマックスへの助走。
この「SPAWN」は、リッチー・ホウティンによるアシッド志向を全面に押し出したユニット名義。
硬質なビートの中に、過激な音響実験とアシッドラインが絡み合う、彼の攻撃的な一面が色濃く反映されたプロジェクト。
デトロイト・テクノのレジェンドUnderground Resistance(UR)からリリースされていたROBERT HOOD「Museum」から、まるでヘヴィ・メタルのギターリフのように鋭く、重圧なシンセが容赦なく反復するSolfurex「Point Break」でフィニッシュ。
全25曲、若さと勢いがそのまま反映された、押し切るようなハード・ミニマルの連続。
DJ歴わずか4年で、日本初のDJ MIX CDを完成させてしまう田中フミヤの底知れぬセンスと集中力が詰まっている。
今の成熟したフミヤ氏からは想像できないほどハード一直線。
だが、その潔さこそがこの時代のテクノの魅力でもあり、20年以上経った今もまったく古びていない。
むしろ、今だからこそ聴き返したい名盤。
↓田中フミヤのハードミニマル時代の決定版
デジタルDJ入門に最適DDJ-400の後継機種↓